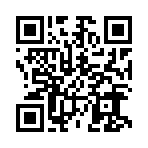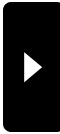2012年06月14日
かわらの歴史①
こんにちは
いつもひんやりするかわらミュージアム館内ですが、さすがに今日は暑い
明日からまた梅雨模様に戻るようなので、貴重な日差しですね
さて、今日はすこーしだけ、かわらの歴史について紹介します
かわらの歴史はざーーーーっくりいうと、
① 588年に百済より伝来して宮殿や寺社に使用される
↓
② 今から<4~500年ほど前に城郭建築に使用され始める
↓
③ 今から300年ほど前に一般的に普及が始まる
という感じです
伝来が、588年。
仏教の伝来と共にかわら博士も日本に来日。
仏経をとりいれた飛鳥文化の建築物が作られ、かわら博士の指導の下、日本の職人が作る。
日本には、縄文土器などがあったし、案外すぐに瓦の技術を習得したものと
思われているみたいです。
また、軒丸瓦の紋様など、デザインは特に優れ 、
、
いまにしてまねできない瓦もたくさんあるとのこと!
さすが、日本人や~
この頃は、寺社建築に主に用いられ、少し後に、宮殿建築にも用いられるようになったそう。
主に、権威としての使用だったけれど、後に防火の観点からも、寺社の宝物殿などにも
用いられるようになったといわれています。
さて、伝来当初、権威としての使用が主で、今日のように普及していない、かわら。
どのような歴史を経て、今のように民家への使用まで至ったのでしょうか

そして、八幡瓦はどのように生まれ、発展していったのか

私も勉強しながら、綴っていきたいと思います
(更新は超不定期です )
)
では、今日はこの辺で・・・・

いつもひんやりするかわらミュージアム館内ですが、さすがに今日は暑い

明日からまた梅雨模様に戻るようなので、貴重な日差しですね

さて、今日はすこーしだけ、かわらの歴史について紹介します

かわらの歴史はざーーーーっくりいうと、
① 588年に百済より伝来して宮殿や寺社に使用される
↓
② 今から<4~500年ほど前に城郭建築に使用され始める
↓
③ 今から300年ほど前に一般的に普及が始まる
という感じです

伝来が、588年。
仏教の伝来と共にかわら博士も日本に来日。
仏経をとりいれた飛鳥文化の建築物が作られ、かわら博士の指導の下、日本の職人が作る。
日本には、縄文土器などがあったし、案外すぐに瓦の技術を習得したものと
思われているみたいです。
また、軒丸瓦の紋様など、デザインは特に優れ
 、
、いまにしてまねできない瓦もたくさんあるとのこと!
さすが、日本人や~

この頃は、寺社建築に主に用いられ、少し後に、宮殿建築にも用いられるようになったそう。
主に、権威としての使用だったけれど、後に防火の観点からも、寺社の宝物殿などにも
用いられるようになったといわれています。
さて、伝来当初、権威としての使用が主で、今日のように普及していない、かわら。
どのような歴史を経て、今のように民家への使用まで至ったのでしょうか


そして、八幡瓦はどのように生まれ、発展していったのか


私も勉強しながら、綴っていきたいと思います

(更新は超不定期です
 )
)では、今日はこの辺で・・・・

Posted by あすナビのブログ at 14:24
│かわらミュージアムのあれこれ